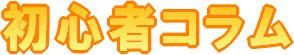バイオリン弦の交換方法(張り替え)、種類、寿命などをご案内します。
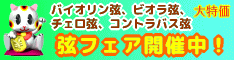 バイオリン弦、ビオラ弦、チェロ弦の販売コーナーはこちらです→→→
バイオリン弦、ビオラ弦、チェロ弦の販売コーナーはこちらです→→→
本ページでは、弦の種類、性質、取扱い、選び方、交換方法(張り替え)などを以下に詳しくご案内しますので、ぜひご参考ください。
弦の種類
◆ガット弦・・・弦本来のスタイルを継承
古くから、あらゆる弦楽器の弦として広く使われてきました。
羊の腸から強い繊維を取り出して乾燥させ、よじり合わせたものです。
現在ではそれを芯材として、糸状の金属を巻き付けたもの(巻線)までを総称してガット弦といいます。
しなやかさが特徴で、音が豊かで柔らかく、あたたかみがあります。
その音質はたいへん魅力的で、他の素材の弦にはない独特の音質に惚れ込んで愛用している人も少なくありません。
古くから高級弦として使われますが、温度や湿度の影響を受けやすく、伸びやすいためチューニングが困難で寿命も短く、お値段も比較的高価格です。
また、ガット弦で美しい音色を奏でるためには、相応のボーイング技術が必要な弦でもありますので、中上級者の方におすすめします。
◆スチール弦・・・安定性、耐久性が持ち味
ガットに代わる素材として開発された弦で、金属の線が用いられています。
しなやかさや音の柔らかさでは劣りますが、十分な音量を得ることができます。
伸びにくいため、安定性や耐久性に優れ、チューニングが容易であることが特徴です。
寿命が長くて取り扱いやすく、また低価格なため、初心者の方を中心に、中学高校のオーケストラで、また子供用分数バイオリンにも多く使われます。
他の素材の弦と比較すると音色は金属的な印象を受けますが、クリアで明るい音を好む人には好評です。
特にチェロ弦においては、スチール弦が圧倒的に人気です。
◆ナイロン弦・・・現代の主流
その名の通り芯材がナイロンの巻線です。ナイロンといっても実際には様々な合成繊維が使われています。
芯材の構造や、その芯材に巻かれる巻線の金属も各メーカーが工夫を凝らし、弾きやすく様々な音質を産み出しています。
ガット弦の柔らかな音色を目指しながら、チューニングの安定性などはガット弦より取り扱いやすいため、たいへん人気があります。
また、ガット弦より低価格で耐久性も優れ、ガット弦とスチール弦の長所を兼ね備えた弦と言えるでしょう。
そのため近年ではたいへん人気があり、毎年のように各社メーカーから新製品も発売され、多くの人がナイロン弦を使用しています。
特にバイオリン弦とビオラ弦においては、現代の弦の主流となっています。
1弦(E線)について
バイオリン弦は、細い方から順に1弦、2弦、3弦、4弦ですが、慣れれば一般的にはE線、A線、D線、G線と呼ぶことのほうが多いです。
このうちの、1弦(E線)については、「ボールエンド」と「ループエンド」の2種類のタイプがあります。

「ボールエンド」は、弦の先端部分に丸い金属が付いています。
「ループエンド」は、弦の先端部分は輪っか状になっています。
 「ループエンド」の弦は、ループエンド専用のチューニングアジャスターを使用している場合にのみ使用します(フック状の金具に輪っかを引っ掛けます)。
「ループエンド」の弦は、ループエンド専用のチューニングアジャスターを使用している場合にのみ使用します(フック状の金具に輪っかを引っ掛けます)。
それ以外は基本的にすべて、「ボールエンド」の弦を使用しますが、丸い金属をテールピースの穴やアジャスターの溝に引っ掛けます。
弦の購入時には間違えないようご注意ください(兼用になっている弦もあります)。
ただ、ボールエンドの弦が必要なのに、誤ってループエンドの弦を購入した場合、輪っかをアジャスターに引っ掛ければ、そのまま使用できますのでご安心ください。
ちなみに、2弦(A線)、3弦(D線)、4弦(G線)はすべてボールエンドタイプになります。
弦のサイズについて
分数サイズのバイオリンを使用している場合、バイオリンと同じサイズの弦を使用します(大人用は4/4です)。
一部の弦では、例えば「3/4〜1/2用」といった兼用サイズの弦もあります。
弦が長すぎて糸巻きに巻ききれないことがありますが、その場合は弦の先端をニッパやはさみで適度に切断して使用します。
なお、バイオリンの1/10サイズについては、もともと昔はそのサイズは存在せず、1/8と1/16の間のサイズとして後から設けられたサイズである関係上、多くの弦に1/10用の区分がありません(一部を除く)。
そのためバイオリンが1/10の場合、一般的には1/8用の弦を使用することのほうが多いようですが、弦のテンションの関係上、当店では1/16用の弦を選択されることをおすすめします。
駒への食い込み対策
特にE線は細いため、使用していくうちに弦が駒に食い込んでいきやすいです。
 その対策用として、食い込み防止チューブが付いている弦が多く、使用する場合は左の写真のように、駒に当たる位置にチューブをずらして使用します。
その対策用として、食い込み防止チューブが付いている弦が多く、使用する場合は左の写真のように、駒に当たる位置にチューブをずらして使用します。
他のADG線については、弦自体がそれほど細くないので必要ないでしょう。
駒側に食い込み防止テープを貼る場合もありますが、そういった駒の場合はチューブを使用する必要はありません。
ただ、若干音の響きを抑えてしまう欠点もありますので、こういった食い込み防止対策は敬遠されることも少なくありません。
弦の寿命
まず消耗品である弦は、使用期間に関係なく、突然切ってしまうことも十分にあり得ます。
切れた弦はもう使用できませんので、予備弦を常に用意されておくことを強くおすすめします。
弦が切れなくても、劣化による寿命もあります。
プロの演奏家はだいたい1ヶ月以内には交換するそうですが、趣味として弾く程度でしたら、演奏量にもよりますが、3ヶ月〜半年ほどで交換するのが良いでしょう。
切れなければいつまでも使い続けること自体は可能なのですが、弦が古くなると、音程が取りづらくなり、音の艶もなくなります。弦は定期的に張り替えましょう。
1本だけ切れてしまったら、全体の音のバランスが狂わないよう、できれば全部交換するのが理想ですが、まだ新しければ切れた弦だけを交換しても大丈夫です。
弦は、楽器に張ってから1週間ほどで張力バランスが落ち着き、本来の音質、音色を発揮できるようになると言われています。
そのため、発表会やコンサートなど、できるだけ良い音で演奏したい場合には、直前に交換するのでなく、弦が安定するよう1週間ほど前に交換するのがおすすめです。
また、演奏後には、手汗が付きやすい指板、松脂が付着するボディだけでなく、弦もきれいなクロスで拭く習慣をつけることで、発錆や劣化を遅らせることができます。
バイオリン購入時に張ってある弦
低価格帯のバイオリンにはじめから張ってあるノーブランドのスチール弦は、コストダウンのため良質なものは少ないです。音質や耐久性が大きく劣るだけでなく、弓毛が引っ掛かりにくいため弾きやすさの面でも劣ります。
高額なバイオリンでも、弦は製造時から張ってあることも多く、演奏しなくても弦は劣化しますので、耐久性は劣ります。
そのため少し使っただけでも切れることもありますが、ギターなど他の弦楽器と同じく、すぐに切れた弦についてのメーカー保証は一切ありません。
当店では、発送前に検品調整を行うため、正常にチューニングができることも間違いなく確認しております。
やはり中にはその時点で切れる弦もありますが、それはもちろん、すぐに切れそうな状態になっている弦も当店の負担にて交換してから発送しております。
しかしながらそれでも、バイオリンの弦自体はもともと切れやすいため、すぐに切れてしまうこともあるかもしれません。
これらのことは特に低価格帯の商品の弦に言えますが、できればすぐにでも、もしくはチューニング等取り扱いに慣れてから、弦を交換することをおすすめします。
音質も耐久性もグンと良くなりますし、弾きやすくもなりますよ。
おすすめの弦は?
当店の取扱商品で、おすすめの弦を教えてくださいとのご質問をよくいただきます。
「弦販売コーナー」をご覧いただくと、たくさんの種類がありますので戸惑うかもしれませんね。
あくまでも個人の好みによりますが、人気度やお手頃価格帯も踏まえて、あえて申し上げますと・・・。
手始めには、扱いやすさ重視であればスチール弦の![]() クロムコアChromcorや
クロムコアChromcorや![]() ヘリコアHelicore、音質も重視されるのであればナイロン弦の
ヘリコアHelicore、音質も重視されるのであればナイロン弦の![]() ドミナントDominantや
ドミナントDominantや![]() インフェルド赤Infeld赤などをおすすめします。
インフェルド赤Infeld赤などをおすすめします。
慣れてきましたら、ぜひとも![]() オブリガートObligatoや
オブリガートObligatoや![]() エヴァピラッツィEvah Pirazziを、更には、上達後にはガット弦の
エヴァピラッツィEvah Pirazziを、更には、上達後にはガット弦の![]() オイドクサEudoxaや
オイドクサEudoxaや![]() オリーブOlivをお試しいただければと思います。
オリーブOlivをお試しいただければと思います。
まだ取り扱い自体がご不安の場合には、音質や耐久性は劣りますが、練習用の安価な弦として、スチール弦の![]() プレリュードPreludeなどが低価格です。
プレリュードPreludeなどが低価格です。
以上、ごく一部の商品をご案内しましたが、実際には、バイオリン本体の性質や演奏者の奏法やスタイルにより音色は変わり、なにより個人の主観によりますので、ベストな組み合わせといったものは存在しません。
いずれにしましても、様々な弦の違いによる様々な音色の違いをお試しいただくことも、たいへん興味深いものですので、バイオリンの上達とともにじっくりとお楽しみいただければと思います。
弦の交換方法(張り替え)
先述したとおり弦は消耗品ですので、また決して難しい作業ではありませんので、ご自身で弦を交換できるようにされることをおすすめします。
まずご注意いただきたいのは、すべての弦を同時に外してはいけません。
駒を倒さないよう、また魂柱が倒れないようにするために、弦は1本ずつ交換していきます。
ボディ内部にある魂柱は接着されているわけではなく、ただ挟まっているだけで(「魂柱について」参照)、通常は弦の圧力によってしっかりと固定されますが、すべての弦を外すと、魂柱の位置がずれたり倒れたりする可能性があるのです。
とは言っても、よほどのことがなければ大丈夫ですので、あまり神経質にならなくても結構ですが、できれば1弦(E線)、4弦(G線)、2弦(A線)、3弦(D線)の順番で、1本ずつ交換する習慣をつけておくと安心です。
交換する際には、駒の傾きにも常に注意しながら行うようにしましょう。駒の正常な状態については、「駒について」をご参考下さい。
更にもう一つ、慣れないうちは作業中にうっかり手を滑らしたりすることもあるでしょう。その際、ピンと張った弦が勢いよく一気に緩んだ拍子に万が一顔に当たると危険ですので、必要以上に顔を近づけて作業しないようにしましょう。
以上を念頭に置き、それでは糸巻きを緩めて弦を1本外してみましょう。
余談ですが、弦を外したついでに、駒や上駒の弦が通る溝に、濃い鉛筆やロウをなぞっておくと、滑りが良くなり弦を傷めにくくなりますよ。


次に新しい弦を取り付けます。
 弦の丸い金具を「テールピースの穴」や「アジャスターの溝」に引っ掛けます。
弦の丸い金具を「テールピースの穴」や「アジャスターの溝」に引っ掛けます。
このときもし、弦の巻き糸部分が太くて入りにくい場合は、ボールペンの先などでキュッキュッと押し込んで入れたり、太い巻き糸部分をラジオペンチなどで押さえ細く整えていただくことで簡単に入れることができます。
もう一方の先端を、糸巻きに巻き付けていきますが、この巻き付け方にも注意が必要です。
 弦の先を糸巻きの穴に通し(糸巻きの反対側から少しはみ出る程度まで入れます)、手前から奥へとグルグル巻いていきます。
弦の先を糸巻きの穴に通し(糸巻きの反対側から少しはみ出る程度まで入れます)、手前から奥へとグルグル巻いていきます。

 弦がすぐに抜けてしまうときには、穴の反対側から出した弦の先端を挟み込むか、一度交差させるのが望ましいです。
弦がすぐに抜けてしまうときには、穴の反対側から出した弦の先端を挟み込むか、一度交差させるのが望ましいです。
 そして、弦が重ならないよう、内側から外側に巻いていきます。
そして、弦が重ならないよう、内側から外側に巻いていきます。
弦が重なっている状態で巻くと、そこで弦が擦れ合い、簡単に切れてしまうことがありますのでご注意ください。
なお、特に分数サイズの場合には、弦が長すぎて糸巻きに巻ききれないことがありますが、その際は一旦弦を外し、弦の先端をニッパやはさみで適度に切断して使用します。
 ある程度まで巻いたら、駒と上駒の溝にちゃんと通るように弦をずらして、糸巻きをゆっくりと巻くようにします。
ある程度まで巻いたら、駒と上駒の溝にちゃんと通るように弦をずらして、糸巻きをゆっくりと巻くようにします。
弦は横方向の力には強いのですが、縦方向の力には弱く、急激に強く巻くと、駒や上駒の辺りなどで切れてしまうことがありますのでご注意ください。
そしてあとはチューニングをして完了ですが、これについては「チューニング方法」をご覧ください。